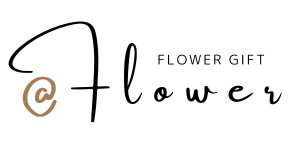気心の知れた友人から「ちょっと面白い店があるんだ」と声をかけられ、気軽な気持ちで出かけた夜のことだった。先斗町の入り組んだ細い路地を進んでいくと、ひっそりと佇む一軒の酒場に辿り着いた。

古びた木製の引き戸をくぐると、店内にはどこか懐かしい昭和の駄菓子屋を思わせる空気が漂っていた。薄暗い電球の明かりがぼんやりと店の隅々まで広がり、壁には色褪せたポスターや、昔ながらのキャラクター商品が雑然と並べられている。カウンターの上には見たことのある駄菓子風のおつまみがいくつも並べられ、色とりどりのパッケージが妙に目を引いた。これがいわゆる“突き出し”だと知り、思わず微笑してしまった。
「変わってるだろ?」と、友人が言う。
ほろ酔い気分でメニューを眺めていると、次々と人が入ってきた。友人が招いたという台湾人のグループだった。彼らは気さくな雰囲気をまとい、片言の日本語を交えながら賑やかに自己紹介を始める。友人は、仕事で台湾に何度も訪れており、いつしか彼らと気の置けない仲になったのだという。
その夜、店は異国の香りを纏い、どこか不思議な一体感に包まれていった。話が進むにつれて、酔いの勢いも手伝い、笑い声が途切れることはなかった。異文化や日本の風習について語り合い、普段は触れられないようなトピックに話が弾んだ。
しかし、酔いが深まった頃だった。何気なく口にした一言、
「あ……」
ふと気づいた時には、すでに遅かった。その言葉が台湾人の彼ら、そして友人にどう映ったのか、酔った勢いで流されたものの、後からじわじわと胸の中に後悔の波が押し寄せてきた。無意識に口にした言葉の一つが、差別的なニュアンスを含んでいたのだ。
彼らは笑って受け流してくれた。あるいは酔いのせいで、そのまま忘れられてしまったのかもしれない。しかし、自分の心の奥に渦巻く後悔と自己嫌悪は、酔いが醒めるにつれて一層鮮明になっていった。
「なんて愚かなことをしてしまったんだろう……」
普段なら絶対にそんなことは口にしないと思っていた自分が、知らず知らずのうちに心の奥に潜む偏見を晒してしまった。その無自覚さが、何よりも恐ろしかった。友人が繋いでくれた縁を、僕は一瞬のうちに壊しかねない言動をしてしまったのだ。
席を立つ頃、台湾の彼らも友人も笑顔を見せていた。何もなかったかのように肩を叩き合い、「また飲もうな」と言葉を交わして別れた。しかし、胸に残る後味の悪さは、どうしても拭い去ることができなかった。
その夜、家に帰ってからも、薄暗い酒場の光景が頭から離れなかった。静まり返った部屋で、僕は天井を見つめながら自問する。
「本当に自分は、相手のことを尊重できていたのだろうか?」
ふと浮かんだ台湾の彼らの表情。その笑顔が、どこか苦笑いに見えたような気がしてならない。言葉の重さと、自分の無自覚な愚かさを噛み締めながら、僕は深い自己嫌悪の中で夜を過ごした。
そして、さらに思いを巡らせる。「この無意識の中に潜む差別心は、いつからできあがってしまったのだろう? どうしてこんな感情が自分の中に育ってしまったのか……」。何も考えずに発した言葉の裏に、どこかで刷り込まれてしまった偏見が隠れていたのかもしれない。それを思うと、自分自身がとても情けなく、悲しくなった。
自分では決してそんな考えを持っていないつもりだった。それなのに、どうしてこんな心の闇があるのだろう。根拠もなく浮かび上がってしまう偏見や誤解。それは、自分が今までどこかで見てきたもの、あるいは聞いてきたものの積み重ねが、知らぬ間に心の奥底に沈殿してしまったものなのかもしれない。
それを考えれば考えるほど、悲しさと寂しさが胸の中で膨れ上がっていった。自分の中に育ってしまった「無意識の差別」という見えない影。それを抱えたまま、彼らと本当に対等に接することなどできるのだろうか? その問いは、いつまでも僕の心に残り、夜が明けても消え去ることはなかった。